廃村・過疎集落探訪体験記 No.8
漁村の廃村・歩古丹集落跡探訪

海辺の崖の縁に建つ,旧歩古丹(Ayumikotan)小学校の校舎です。
-
-

 漁村の廃村・歩古丹集落跡探訪 〜 北海道増毛町
漁村の廃村・歩古丹集落跡探訪 〜 北海道増毛町
-
北海道在住の成瀬健太さんからの報告で,時期は2009年5月,場所は北海道増毛町の歩古丹(Ayumikotan)という漁業集落跡です。
=====
増毛町歩古丹。恥ずかしながら,一番最初に見たときは「ほこたん?」と読んでしまいました。正しくは「アユミコタン」という名前です。様々な解釈がありますが,アイヌ語で元々は「アエヒコタン」という名前で(アエヒ:アワビ,コタン:集落)『あわびが採れるところ』という意味だそうです。
歩古丹は数ある廃村でも珍しい,漁村の廃村であることです。北海道内で,漁業関係の廃村地域は積丹町浜婦美,神恵内村オブカル石,北檜山町(現せたな町)日中戸しかありません。
その数少ない漁村の廃村,歩古丹。探訪しようかどうか悩んでいましたが『簡単に足を運べない地域』であることを考え,探訪を決意しました。
当初は単独で行く予定でしたが,いつぞや合同探索でお世話になった井手口さんが来道されるとのことで,二人で歩古丹へ行くことになりました。
漁業関係の廃村,「学校跡を有する廃村」という条件で,離島を除いて絞り込むと,北海道の日本海側,歩古丹,浜婦美,オブカル石,日中戸の4ヶ所となります(本州,四国,九州にはありません)。農業,畜産業,林業などと比べると,漁業の経済基盤は強いことがわかります。
私は,日中戸には昭和63年8月に行ったことになっていますが,手前の水垂岬の灯台までで,集落跡にはたどり着いていないようです。
ちなみに井手口さん(きたたびさん,「北海道旅情報」Webの管理者)とは,平成19年3月,愛知県設楽町の廃村 宇連を合同探索しました。世間は狭いものです。

井手口さんとお会いする前日(2009年5月2日),増毛に到着して郷土資料・図書館の『元陣屋』へ行き担当職員に質問します。担当職員は些か驚いていましたが,やがて歩古丹が舞台になった映画のことを教えてくれました。
映画名は『ジャコ萬と鉄』(1949年)で,歩古丹にあった『南出漁場』が撮影に全面協力してくれたとのことです。ロケセットの可能性もありますがかつての歩古丹の様子,ニシン漁の厳しさ,そしてニシンの群来シーンは一見の価値があります。
この日は増毛駅から程近いところの旅人の宿「ぼちぼちいこか増毛館」に宿泊。「旅人の宿」と云うことでクルマで関西から来た人,鉄道で来た人,さらに自転車で来た人もいて賑やかでした。
翌5月3日,宿の人と別れた後井手口さんとお会いし,いよいよ歩古丹へ。
既存の探訪レポートもあるとは云え,本当にあるのか?と思っていましたが現地を見て驚きました。
晴れていたとは言え風が強く,眼前に日本海が広がり「猫の額」ほどしかない僅かな平地に「へばり付くように」建っている校舎がそこにありました。井手口さんも校舎を見て感動するよりも驚いていました。
急な斜面をくだり,ようやく降りた先には建物の基礎,焼酎のビン,食器を含めたセトモノが散乱していました。
やはり歩古丹は,ニシン漁で栄えた漁村だったのですね。ニシン漁の最盛期は明治30年代(漁獲量97万トン/年,M.30)。『ジャコ萬と鉄』の頃は,まだ20万トン/年(S.24)の漁獲量がありましたが,昭和30年代以降は数千トン/年の年がほとんどです。
歩古丹小学校は,児童数10名(S.34),へき地等級5級,昭和46年閉校。険しい地勢の海辺の集落が,昭和46年まで存続したというのは,驚くべきことです。

早速校舎に入りましたが長年の風雪により床は波打ち,抜けているところもあります。黒板を見れば記念の書き込みの類があります。しかしよく見れば,かつて歩古丹小学校校長先生として勤務されていた方,さらに近郊の小中学校遠足で来た書き込みがありました。校長先生の書き込みは平成の初期,遠足の書き込みはもっと前の昭和50年代です。

風雪により倒壊した便所棟では達筆な字で書かれた「便所用」バケツ,倒れた小便器,さらに校舎のすぐ横には,錆びたブランコが植物と一体化しながらも原形を留めていました。校舎裏には教員住宅と思われる基礎が残されていました。
歩古丹は地勢だけではなく,気象も厳しそうです。そのような環境の中,閉校から38年も校舎が残っているというのは驚きです。残っているうちに,私も訪ねてみたいものです。

学校跡から増毛方面へ歩くと番屋跡がある,と言う情報を事前に入手していたので番屋を目指して歩きました。海岸は石がゴロゴロ転がり非常に歩きにくく,辺りは漁具やゴミ,さらにハングル文字のヘルメットなどが打ち上げられていました。
番屋跡に到着しましたが,既に瓦礫と化し往時を偲ぶものは,傍に倒れていた「木製電柱」くらいでした。もしかしたらここが「ジャコ萬と鉄」で全面協力した「南出漁場」跡なのかもしれません。
往時の歩古丹の交通は船が主で,徒歩交通(山道)はほとんど使われていなかったそうですね。海沿いのR.231が全通したのは昭和56年,冬季を含む通年の開通は平成4年とのこと。
平成4年夏には,増毛から歩古丹を通過して,雄冬,小樽へとバイクで走りましたが,かつては海路しかない「陸の孤島」だったという雰囲気は感じられませんでした。
新しい道路の存在を無視しなければ,50年ほど前の暮らしは想像できそうにありません。今も番屋跡や船泊の跡が見られるというのは,廃村ならではなのかもしれません。

帰り際,ふと海を見ればかつて船を停泊させていたと思われる船泊の跡が波に洗われながらも存在を誇示していました。
後日,昭和40年代に増毛高校で教鞭を執っていた方と電話したとき,「あんたもよく行ったねぇ」と笑いながら歩古丹について教えてくれました。
昭和40年代当時,雄冬まで行けば整備された漁港がありましたが,歩古丹は小さな船でないと行けない場所で,ニシン漁で生計を立てていた場所でした。その頃,雄冬地区は「西の知床」と呼ばれていたほど「陸の孤島」で,増毛からの定期船でしか行けない地域でした。歩古丹もそれに準ずる地域でした。
増毛−雄冬の海路は定期航路(平成4年春まで存続)だったことを考えると,歩古丹のへき地度は,雄冬よりも高かったのではないかと思われます。集落が存続していた頃,旅で訪ねる方は皆無だったのではないでしょうか。
私が初めて北海道に出かけたのは,昭和56年夏(当時19歳)。その時は,最果ての地を目指して稚内,礼文島まで行きましたが,歩古丹は間違いなく礼文島よりも最果てですね(^_^;)
成瀬さんからの投稿は,名寄市北山(平成18年9月)以来二度目です。北山にはその一年後,成瀬さんと一緒に訪ねる機会を得ましたが,今回はどうでしょうか(^^)
いつかまた,合同探索,飲み会などしたいものです。投稿いただき,感謝します。
参考文献
・増毛町史 増毛町史編纂委員会 昭和49年
・東宝映画「ジャコ萬と鉄」監督 谷口千吉 主演 三船敏郎/月形龍之介/久我美子 1949年
・明治期の増毛町俯瞰図及び昭和20年代俯瞰図(文化総合交流促進施設 元陣屋収蔵資料)
(C) 06/27/2009
 「廃村・過疎集落探訪体験記」ホーム
「廃村・過疎集落探訪体験記」ホーム
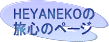


| 
 漁村の廃村・歩古丹集落跡探訪 〜 北海道増毛町
漁村の廃村・歩古丹集落跡探訪 〜 北海道増毛町
 「廃村・過疎集落探訪体験記」ホーム
「廃村・過疎集落探訪体験記」ホーム